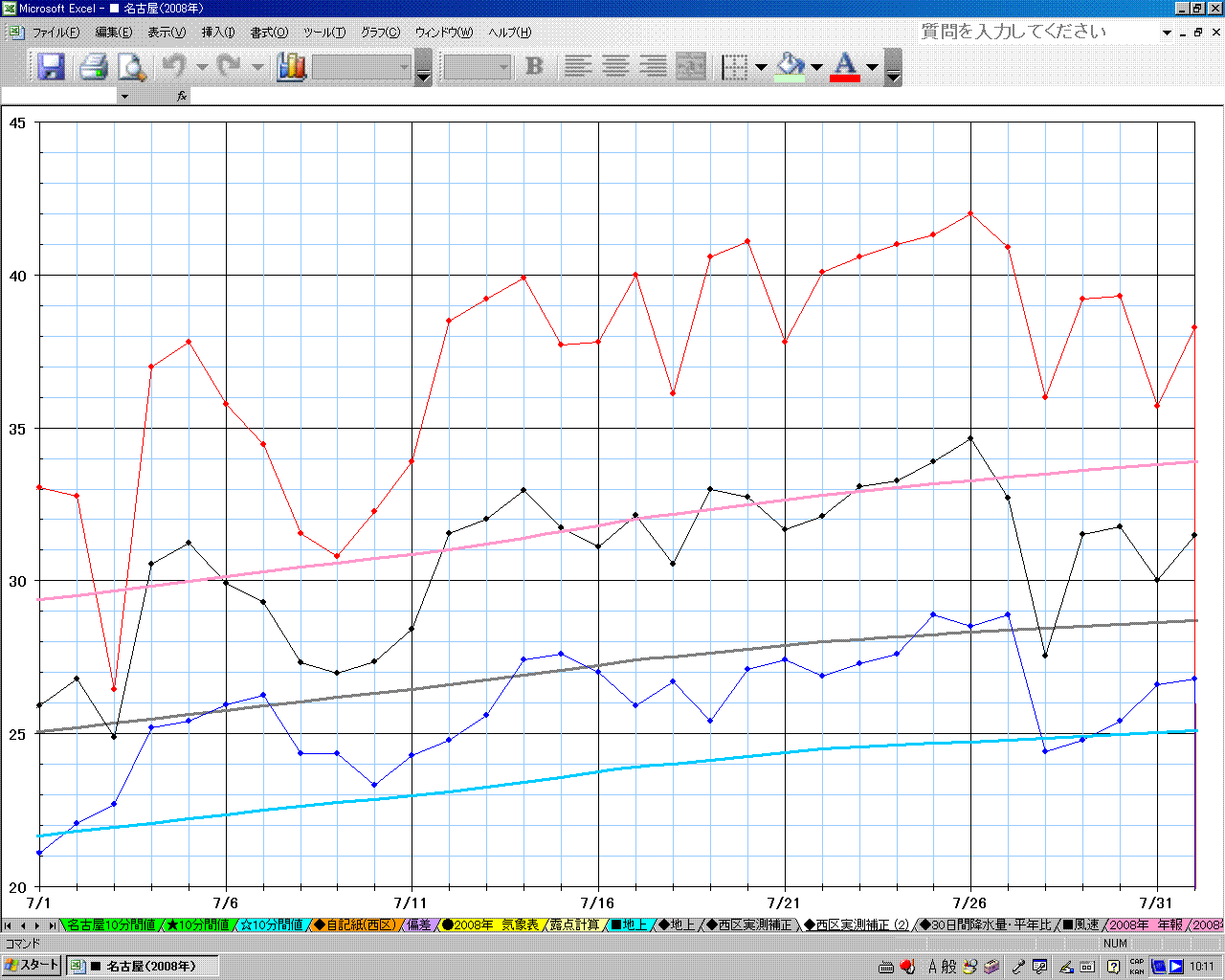 当地の7月の気温を紹介します。
当地の7月の気温を紹介します。
現在は測器の老朽化で自記温度計は使用していませんが、最高・最低温度計を使って気温の監視は続けています。
グラフは、名古屋地方気象台の気温に「係数補正」をした当地の推定値に、さらに5日ごとの当地の最高気温・最低気温の実測値で再補正したものです。
つまり、名古屋地方気象台の観測値を自記温度計の記録として読み取り、当地の実測地から補正値を求めて修正する というイメージです。
気象台と我家は7km程度離れていますから、いつも両者が同じ天気であるとは限らず、しゅう雨のあった日は推定値で1゜程度の推定誤差は現れますが、5日ごとに観測した前5日間の最高気温・最低気温でさらに補正しますとおおむね0.3゜以内で推定できます。
ただ、冬季の最低気温は「接地逆転層」が発達しますと、日の出前の最低気温の現れる時間帯では 当地は気象台より2゜以上冷え込むこともありますからそのようなときはこの推定・補正方法も誤差が大きくなってしまいます。
私は、数年前までの常時観測は測器の老朽化のためやめましたけれど、空調設備の運転の参考にもなりますから気象台のデータを使っていろいろ工夫しています。
工夫するより再度観測を再開したほうが楽ですけれど、健康上の都合(右手が麻痺、その他)もあってなかなか困難です