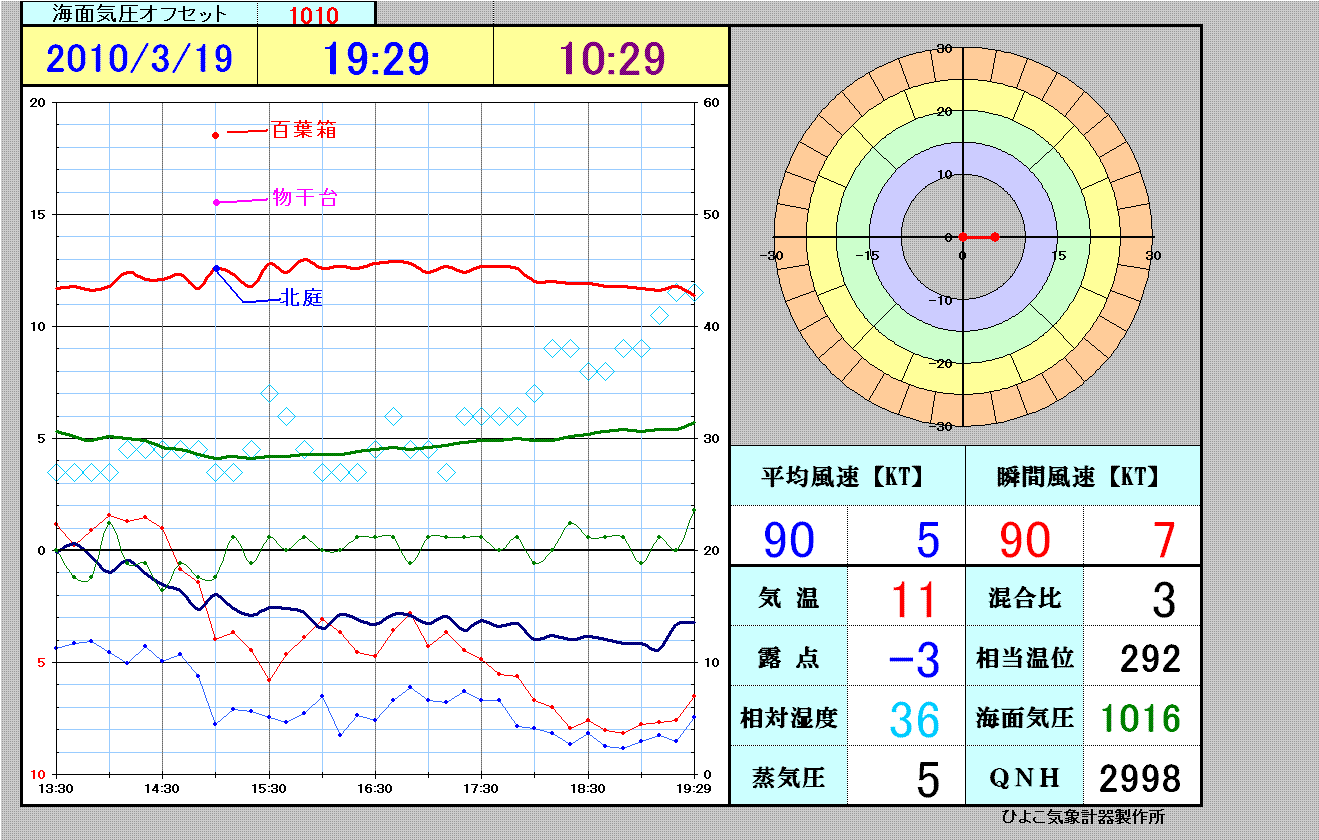 毎年、春・秋には我家では場所によって気温が大きく異なります。
毎年、春・秋には我家では場所によって気温が大きく異なります。
図は、春日井市消防本部・西出張所(風向・風速は春日井市役所)の気象推移に本日の我家の気温をプロットしたものです。
・ほぼ1日中日陰にならない南庭(公道に面している)の「百葉箱の気温」
・午後から日陰になる地上約5mの「物干台の気温」
・5月〜7月以外は常時日陰の「北庭の気温」(但し5月〜7月でも早朝の朝日と夕方の夕陽だけしか差し込まない)
当然ながら「北庭の気温」は低いですが、盛夏の8月はこの場所は夏至を1ヶ月以上経過して常時日陰になりますけれど、北庭に隣接している隣家の庭の影響もあり、南庭の百葉箱の気温とほぼ同じ(暑さ)になります。
一番風通しのいい「物干台」は仮にその場所に百葉箱を設置したとしても、午前と午後で日当りが大きく異なるために観測に適さず、物干台の近くの屋根の軒下などに温度計を設置して仮観測したこともありますが、ステンレス通風筒などで屋根の照り返しを遮っても45゜近くなってしまうため、やはり南庭の百葉箱の場所の気温が一番妥当として記録しています。
住宅密集地での気温観測の困難さは40年続けても、「この方法が一番自然の気温に近い」という場所を探すことは困難でして、一時は風向風速計の場所(地上10m)も検討しましたけれど、瓦屋根に上がってメンテナンスするのは非常に危険ですし、仮にその場所に設置しても屋根瓦上2mですから、特に盛夏は気温が高めに現れてしまう可能性もあります。
以上、毎年この時期に感ずる「個人の家庭の敷地内のどこで気温を計るのが一番自然に近いか」という悩みを紹介しました。人間は通常地上で生活していることを考えれば、やはり「百葉箱」の位置が妥当か。(但し中・高層住宅居住者を除く)
家屋の周囲が隣家と10mぐらい離れていればいいのですが、我町内ではそうもいかず。(窓ごしに隣の奥様と握手ができてしまうほど密集していますから)